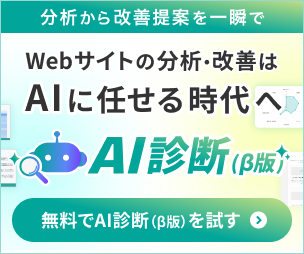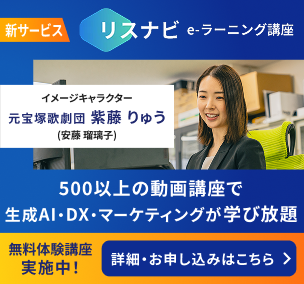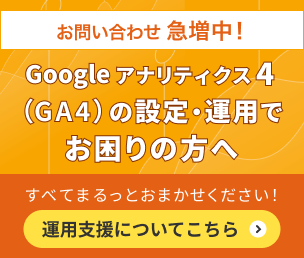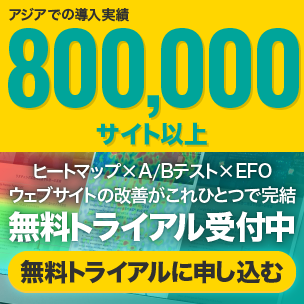ファネル分析とは?コンバージョン率が改善する活用事例やおすすめのツールを紹介
- ・アクセスは多いのにCVRが上がらない
- ・顧客がどの段階で離脱しているのか特定できない
- ・ファネル分析のやり方が知りたい
ファネル分析はマーケティングや業務プロセスの改善に活用される基本的な分析手法です。ファネル分析を行うことで顧客が離脱している箇所を可視化でき、Webサイトの改善点を特定できます。
この記事ではファネル分析のメリットや活用事例、具体的な実践方法について解説します。記事を読めばファネル分析によりWebサイトのボトルネックを特定し、CVRを向上させる具体的な施策を打つことが可能です。
Webサイトの離脱ポイント(ボトルネック)となっている箇所を改善することが、CVR向上の最短ルートです。ファネル分析を行えば顧客の行動を段階的に捉え、ボトルネックを特定できます。
目次
- ファネル分析は顧客の行動を分析してボトルネックを特定する手法
- ファネル分析の種類5選
- ファネル分析が古いと言われる理由
- ファネル分析、4つのメリット
- ファネル分析を実践する流れ
- ファネル分析の注意点
- ファネル分析の活用事例
- ファネル分析におすすめのツール
- GA4 AIレポート®でできること
- GA4 AIレポート®を導入してボトルネックを改善しよう
ファネル分析は顧客の行動を分析してボトルネックを特定する手法

ファネル分析とは顧客が商品やサービスを知ってから購入・申し込みまでの流れを可視化する手法です。顧客の数が各段階で減っていく様子が漏斗(じょうご=ファネル)の形に似ていることから、ファネル分析と名付けられました。
例えば、BtoBサイトでは「アクセス→サービス閲覧→フォーム入力→送信完了」といった流れをファネル分析し、ボトルネックを特定します。
ファネル分析を活用すれば「CVRが上がらない」などの漠然とした課題の原因を特定し、効果的な改善施策を立てられます。
ファネル分析の種類5選

ファネル分析には複数の種類があります。顧客の行動がインターネットの普及によって複雑化しているため、単一の分析モデルだけでは全体像を把握しきれないからです。ビジネスの目的や顧客との関係性に応じて、適切なファネル分析の選択が求められます。ファネル分析の種類は以下の5つです。
- ・パーチェスファネル
- ・インフルエンスファネル
- ・ダブルファネル
- ・ルーピングファネル
- ・マイクロモーメントファネル
パーチェスファネル
パーチェスファネルとは顧客が商品やサービスを知ってから購入に至るまでの行動を、段階的に示した最も基本的なファネルモデルです。
顧客は商品を知る「認知」から、興味・比較・検討を経て、最終的に「購入」に至るまでの過程をたどります。認知から購入に進むにつれて、対象となる顧客の数が徐々に減少していくことが一般的です。Webサイト運営における各段階では、以下のような施策が考えられます。
- ・認知段階:SEO対策や広告を活用し、商品・サービスの存在を広く知ってもらう
- ・興味・関心段階:ブログ記事やSNSで有益な情報を発信し、興味を深めてもらう
- ・比較・検討段階:導入事例や顧客の声を掲載し、他社との差別化を伝える
- ・購入段階:入力フォームの最適化などにより、スムーズに購入を完了できる環境を整える
パーチェスファネルはさまざまなファネルモデルの基礎となっています。
インフルエンスファネル

インフルエンスファネルとは商品購入後の「共有」や「拡散」といった行動を重視するファネルモデルです。SNSの普及により消費者の口コミやレビューが、他の人の購買行動に大きな影響を与えるようになりました。
パーチェスファネルが逆三角形で顧客数の減少を表すのに対し、インフルエンスファネルは三角形のような形で情報の拡散を表します。インフルエンスファネルでは、購入後の口コミや紹介によって影響の範囲が広がっていく様子を示しているからです。
インフルエンスファネルでは顧客をファン化し、商品の良さを広めてもらう「推奨者(アドボケイト)」に育成することを目指しています。
ダブルファネル
ダブルファネルはパーチェスファネルとインフルエンスファネルを組み合わせたモデルになります。購買前後の両方を一体的に設計し、長期的な売上(LTV)最大化と口コミによる新規獲得を両立できる点がダブルファネルの特徴です。ダブルファネルの構成は以下のとおりです。
| 区分 | ファネル名 | 主なプロセス | 目的 |
|---|---|---|---|
| 前半 | パーチェスファネル | 1.認知 2.興味・関心 3.比較・検討 4.購入 |
新規顧客の獲得・購買促進 |
| 後半 | インフルエンスファネル | 1.継続利用 2.推奨・紹介 3.SNSでの発信 |
既存顧客のファン化・拡散促進 |
ダブルファネルとは新規顧客の獲得から既存顧客の維持・拡散まで、マーケティング効果を一貫して可視化できる分析モデルです。
ルーピングファネル

ルーピングファネルは顧客の購買行動が一度きりで終わらず、購入後も繰り返し循環するという考え方にもとづいたファネルモデルです。
ルーピングファネルは顧客と長期的な関係を築き、継続的な売上につなげることを目的とします。新規顧客を増やすだけでなく既存顧客の満足度を高めて再利用につなげることが、ビジネスを長く続けるためのポイントです。
ルーピングファネルでは「認知」「検討」「購入」といった従来の段階に、購入後の行動である「利用」と「推奨(共有)」を加えます。利用は顧客が実際に商品やサービスを使い、価値を体験する段階を指します。推奨(共有)は体験に満足した顧客が友人や家族、SNSなどを通じて、製品やサービスの良さを広める段階です。
ルーピングファネルはECサイトやサブスクリプション型サービスなど、既存顧客との関係づくりが重要なビジネスで特に有効です。
マイクロモーメントファネル
マイクロモーメントとはGoogleが示した消費者が「〜したい」という、行動を起こす瞬間的な欲求に焦点を当てた概念です。現代の消費者は商品購入までの道のりが一直線ではなく、欲求が生まれた瞬間にスマートフォンで検索して行動を決めます。代表的なマイクロモーメントは以下のとおりです。
| 区分 | 顧客の心理・行動 | 内容 |
|---|---|---|
| Know (知りたい) | 疑問を解決したい・情報を知りたい | 疑問や悩みを解消するために情報を検索・収集する段階 |
| Go (行きたい) | お店や施設の場所への行き方を調べたい | 目的地や行動先を明確にし、訪問・体験を検討する段階 |
| Do (したい) | 何かをしたい・やり方を知りたい | 具体的な行動や方法を実行に移すために情報を求める段階 |
| Buy (買いたい) | 商品やサービスを購入したい | 比較・検討を経て、購入・契約など最終的な意思決定を行う段階 |
Googleが提唱するマイクロモーメントの考え方に沿って作られたファネルがマイクロモーメントファネルです。顧客がWebサイトを訪れる目的を正確に把握して欲求に即した情報を提供することで、離脱を防ぎCVRの向上につなげられます。
» Google「マイクロモーメント」(外部サイト)
ファネル分析が古いと言われる理由

スマートフォンの普及によって購買行動が大きく変化し、従来のファネル分析は古いと感じる人も増えています。ファネル分析が古いと言われる理由を、以下の項目に分けて解説します。
- ・消費者のニーズや価値観の多様化
- ・消費者の購買行動の多様化
消費者のニーズや価値観の多様化
消費者のニーズや価値観が大きく変わった点が、従来のファネル分析が時代に合わなくなってきた理由の一つです。消費者は企業からの情報だけでなく口コミや個人の感想を参考に、自分なりの基準で商品やサービスを選ぶことが当たり前になっています。現代の消費者が重視する価値観は以下のとおりです。
- ・購入を通じて得られる特別な体験やブランドへの共感
- ・環境や社会に配慮した企業から商品を買いたいという意識
- ・自分の趣味やライフスタイルに合った商品
消費者のニーズや価値観の多様化がファネル分析が古いと言われる一因になっています。
» 消費者庁「消費者意識基本調査」(外部サイト)
消費者の購買行動の多様化
現代の消費者は一直線の決まったルートで商品やサービスを購入しなくなりました。スマートフォンやインターネットが広く使われるようになり、誰でも手軽に情報を集められるようになったためです。
昔は「広告を見て店で買う」といった単純な流れが一般的でした。しかし、現代では消費者が情報を探す場所はSNSや比較サイト、動画など多岐にわたります。消費者の購買行動は一方向ではなく複雑に入り組んでおり、従来のファネル分析では実態を正確に捉えることが難しくなっています。
» 消費者庁「インターネットを介した様々な行動の変化」(外部サイト)
ファネル分析、4つのメリット

顧客行動が多様化し、購買プロセスが複雑になった現代においても、ファネル分析は依然として有効な手法です。ファネル分析のメリットについて以下の4点を解説します。
- ・顧客の離脱ポイントを特定できる
- ・CVR(コンバージョン率)の向上に役立つ
- ・ペルソナが設定しやすくなる
- ・データにもとづいた判断が可能になる
顧客の離脱ポイントを特定できる

ファネル分析の最大のメリットは、顧客が離脱する箇所を正確に把握できる点です。ファネル分析では商品購入や問い合わせに至るまでの行動を段階ごとに可視化し、各ステップを通過した人数を数値で確認できます。
Webサイト全体の離脱ページだけでなく、入力フォームや未クリックのボタンといった細かな要素までファネル分析で把握可能です。ファネル分析により離脱の原因を明確にする根拠が得られ、Webサイトの構成やデザインを見直す際に有効な判断材料となります。
CVR(コンバージョン率)の向上に役立つ
ファネル分析を行えば各段階での通過率を可視化し、低い箇所を改善することで最終的なゴールに到達する顧客を増やせます。例えば、以下のような施策がCVR向上に効果的です。
- ・入力フォームでの離脱が多い→入力項目を減らす
- ・クリック率が悪い→ボタンのデザインや文言を改善する
ファネル分析によって課題のある箇所を正確に特定して的確な対策を講じることで、Webサイト全体のCVRを効率的に高められます。
ペルソナが設定しやすくなる

ファネル分析を活用すると、感覚に頼らずデータにもとづいた顧客理解を深められます。Webサイトの訪問者の行動を段階的に追うことで、購入まで進む人と途中で離脱する人の違いを明確にできるためです。
ファネル分析で得た行動データはアンケートなど他の調査手法と組み合わせることで、より精度の高いペルソナ設定に役立ちます。「どの情報を見て購入を決めているか」といった顧客の行動パターンも、ファネル分析を通じて把握できます。
データにもとづいた判断が可能になる
ファネル分析を活用すれば訪問者の行動を数値で見える化し、データにもとづいたマーケティング施策が実行可能です。データを根拠とすることで改善方針の共有が容易になり、社内での合意形成や予算確保も円滑に進みます。
各段階の離脱率を比較して成果を定量的に検証できるため、継続的にPDCAサイクルを推進できる点もファネル分析の魅力です。成果が見込める領域にリソースを集中的に投下すれば、費用対効果が高まり、より精度の高いWebサイト改善につながります。
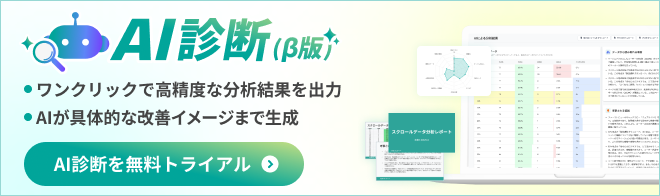
ファネル分析を実践する流れ

ファネル分析を実践する流れは以下のとおりです。
- 1.分析の目標設定と指標を選定する
- 2.顧客の行動データを収集・整理する
- 3.各段階のデータを可視化する
- 4.ファネルチャートで全体像を把握する
- 5.行動フロー図で顧客の動きを追う
- 6.表で具体的な数値を比較する
- 7.データを分けて詳しく分析する
- 8.ヒートマップでページ内の行動を見る
- 9.ボトルネックを特定する
- 10.分析結果をもとに改善策を立案する
分析の目標設定と指標を選定する
ファネル分析を始める前に最終的なゴールと中間目標を具体的に決めることが必要です。ゴールを明確にすることでファネル分析の方向性が定まり、効果的な施策につながります。ファネル分析を行う前に設定しておく項目は以下のとおりです。
- ・最終的なゴール(KGI)の明確化
- ・KGIの具体的な数値目標
- ・顧客の行動フローの定義
- ・中間指標(KPI)の設定
- ・分析の対象の顧客
- ・分析期間の決定
Webサイトの改善の方向性をより効果的に行うために、ファネル分析を始める前に目標と指標を明確に設定しておきましょう。
顧客の行動データを収集・整理する

ファネル分析の目標と指標が決まったら、実際に顧客の行動データを集めて整理する作業に移ります。正確なファネル分析を行うにはデータを一つにまとめることが不可欠です。顧客のデータはWebサイトの分析ツールや顧客管理システムなどに散らばっています。
顧客の行動データを収集・整理することで、精度の高いファネル分析が実行可能です。
各段階のデータを可視化する
集めたデータをグラフや表で可視化すると、課題を直感的に把握しやすくなります。データを図やグラフに整理することで、顧客が離脱している段階やコンバージョン率の低い箇所を一目で確認可能です。各ステップの通過率を棒グラフで表示すると、課題のある部分を直感的に把握できます。
データを視覚的に表現することでファネル分析の結果を直感的に理解でき、関係者間でスムーズに情報を共有できます。
ファネルチャートで全体像を把握する

ファネルチャートは顧客の減少を漏斗(じょうご)型で表現するため、離脱が多い箇所を直感的に確認することが可能です。
例えば、一覧ページから詳細ページへの移行でグラフが細くなっている場合、該当箇所に問題が潜んでいる可能性があります。変化を視覚的に確認することで、改善が必要な箇所をすぐに特定できます。
ファネルチャートによって各段階での離脱状況を把握し、最も改善効果が高いと考えられるボトルネックを特定することが可能です。
表で具体的な数値を比較する
各段階の数値を表にまとめることでグラフでは見落としがちな細かな変化を把握でき、より詳細なファネル分析が可能です。例えば、以下のように表にまとめると問題点の特定に役立ちます。
| 段階 | 顧客数 | 離脱数 | 離脱率 |
|---|---|---|---|
| 商品一覧ページ | 10,000人 | – | – |
| 商品詳細ページ | 6,000人 | 4,000人 | 40% |
| カート投入 | 3,000人 | 3,000人 | 50% |
| 購入完了 | 1,500人 | 1,500人 | 50% |
ファネル分析によって離脱率の高い段階が明確になれば、該当箇所がWebサイトの改善点だと特定できます。
行動フロー図で顧客の動きを追う

多くのWebサイトでは運営者が想定している導線と顧客の実際の行動が一致しないことがよくあります。行動フロー図を使えば想定と現実の差を視覚的に比較し、迷いや離脱が起きている箇所を確認することが可能です。
購入完了ページの直前で前のページへ戻る顧客が多い場合、購入手続きの途中で不明点やストレスを感じている可能性があります。「入力フォームの項目が多い」「支払い方法が複雑」など、顧客の離脱を招く要因はさまざまです。行動フロー図を活用すれば、顧客が迷いやすい箇所や動線の滞りを視覚的に把握できます。
データを分けて詳しく分析する
データを複数のグループ(セグメント)に分けて分析すると、全体の数値だけでは見えない傾向や課題を明確に把握できます。以下のようなセグメントでデータを分けて分析すると、より深い洞察が得られます。
- ・デバイス別分析:スマートフォンとPCでの離脱率の違いを比較
- ・顧客の属性別分析:新規顧客とリピーターの行動を比較し、再訪率や購入傾向を可視化
セグメントごとの比較により顧客の特徴や行動パターンを理解でき、ファネル分析での改善施策の精度を高められます。
ヒートマップでページ内の行動を見る

ヒートマップツールを活用すると、ページ上で顧客がクリックした位置やスクロール範囲を色の濃淡で確認できます。ヒートマップの特徴は興味が集まりやすい領域や、閲覧が止まりやすい部分を直感的に把握できる点です。
ヒートマップ分析で重要な要素への反応が乏しいと判明した場合、デザインや配置を最適化することで成果の向上が期待できます。
» ヒートマップとは?種類・効果・活用事例をわかりやすく解説
ボトルネックを特定する
ファネル分析の目的は顧客が離脱している箇所(ボトルネック)を特定し、改善の優先順位を明確にすることです。ボトルネックを発見するには、以下のような方法で分析を進めます。
- ・数値比較:各段階の通過率や離脱率を比べ、離脱が最も多い箇所を見つける
- ・データ分割:新規顧客・リピーター・年齢層などの違いから、特定の層に課題がないか確認する
- ・経路・デバイス比較:流入経路やデバイス別に成果を比較し、パフォーマンスの低下要因を探る
- ・原因の仮説立て:離脱が多いページの理由を仮定し、行動の背景を分析する
ボトルネックを正確に把握できれば改善箇所が明確になり、限られたリソースで最大の効果を得られます。
分析結果をもとに改善策を立案する

ボトルネックを特定した後は原因を分析し、具体的な改善策を立てます。主な改善策の例は以下のとおりです。
| 改善策 | 内容 |
|---|---|
| ページデザインの改善 | 離脱率が高いページの構成や操作性を見直し、ボタン配置・文言・情報整理を最適化する |
| 手続きの簡略化 | 入力フォームの項目を減らし、支払い方法を増やすなどして顧客の負担を軽減する |
| 再アプローチ施策 | 一度離脱した顧客に対して、広告やメールを活用し再訪を促す |
複数の施策を組み合わせて実行することで、Webサイトの離脱防止やコンバージョン率の向上につなげられます。
ファネル分析の注意点

ファネル分析には注意点があり、見落とすと誤った結論や効果の薄い改善策に陥る恐れがあります。ファネル分析の注意点は以下のとおりです。
- ・市場のニーズをしっかり把握する
- ・BtoCには適さない場合がある
- ・分析にとどまらず実行に移す
- ・部分最適化ではなく全体最適化を目指す
- ・継続的な見直しと調整を行う
市場のニーズをしっかり把握する
ファネル分析を効果的に活用するには市場全体のニーズを正確に理解する工程が欠かせません。ファネル分析はあくまで「Webサイトを訪れた顧客」の行動を可視化する手法であり、訪問前の顧客の心理や市場動向までは把握できないためです。
市場全体の動きを理解して潜在的な需要を把握するためには、以下のようなリサーチを行うことが有効です。
| 分析方法 | 目的 |
|---|---|
| 検索キーワードの調査 | 顧客が抱える悩みや関心を把握する |
| 競合サイトの分析 | 他社がどのようにニーズへ対応しているかを確認する |
| SNSの口コミ・評判の確認 | 消費者のリアルな声や不満点を抽出する |
市場のニーズをしっかり把握することで、効果的なマーケティング施策を実現できます。
BtoCには適さない場合がある

BtoCビジネスでは購買行動が段階的に進まないことも多く、ファネル分析がうまく機能しない場合があります。個人の購買は論理的な判断だけでなく、感情やその場の雰囲気、SNSの情報などにも大きく左右されるからです。
BtoCビジネスでは衝動買いや口コミでの購入など、従来のファネルモデルでは想定されていない動きも多く見られます。Webサイトで商品を見たあと実店舗で購入するなど、オンラインとオフラインを行き来する顧客の行動も一般的です。
BtoCの領域でファネル分析を活用する場合は、顧客の感情的要素や多様な購買経路を踏まえた柔軟な視点が求められます。
分析にとどまらず実行に移す
データを分析して問題点を特定しても、行動に移さなければWebサイトのパフォーマンスは向上しません。ボトルネックを見つけたら「なぜ顧客が離脱しているのか」という仮説を立て、改善策を計画・実行します。ファネル分析により発見したボトルネックの改善施策の例は以下のとおりです。
- ・UI/UXの改善:使いやすさや視認性を高め、顧客が迷わず行動できる設計にする
- ・コンテンツの追加:不足している情報や不安を解消する要素を補う
ファネル分析は課題を発見するだけでなく、改善策を実行して初めて成果につながります。
部分最適化ではなく全体最適化を目指す

ファネル分析では特定の指標だけを改善する「部分最適化」ではなく、顧客体験全体を高める「全体最適化」を意識しましょう。部分最適化による悪影響の具体例は以下のとおりです。
| 施策 | 内容・一時的な効果 | 想定される悪影響 |
|---|---|---|
| 入力項目の削減 | 手続きが簡単になり、離脱率が低下する | 必要な情報が不足し、問い合わせ対応の負担が増加する |
| ポップアップ広告の追加 | 注目度が上がり、一時的にCVRが向上する | 度重なる表示で顧客が不快に感じ、Webサイト全体の印象が悪化する |
個々の改善施策が必ずしも全体に良い影響を与えるとは限りません。顧客の行動は単純な流れではなくページ間で複雑に影響し合うため、Webサイト全体や事業全体のバランスを考慮する必要があります。
全体最適化を進めるうえで欠かせないことがABテストの活用です。例えば、ボタンの色を変えてクリック率が上がっても、購入率や満足度が下がることがあります。ABテストを実施すれば単一の指標だけでなく、体験全体の変化を確認しながら改善を進められます。
» A/Bテストの基本とおすすめのA/Bテストツールを紹介!
継続的な見直しと調整を行う
ファネル分析は一度行って終わりではなく、継続的な見直しと調整が不可欠です。顧客のニーズや市場のトレンドは常に変化しており、分析を放置すると改善策の効果が薄れてしまいます。具体的なWebサイト調整の取り組み事例は以下のとおりです。
- ・アクセスデータの確認:離脱率や滞在時間を分析して問題のあるページを特定する
- ・デザインや導線の改善:ボタン配置や情報の流れを最適化する
- ・A/Bテストの実施:複数のデザインや文言を比較して効果の高いパターンを採用する
ヒートマップやAI解析ツールを活用し、従来見えなかった行動データを把握する手法も有効です。
ファネル分析の活用事例

ファネル分析について以下の3つの活用事例を紹介します。
- ・ECサイトでの活用
- ・BtoB営業プロセスでの活用
- ・SaaSプロダクトにおけるオンボーディングでの活用
ECサイトでの活用
ファネル分析はECサイトにおいて売上向上に直結する有効な手法になります。顧客が商品を認知してから購入に至るまでの過程を可視化し、離脱している箇所を明確にできるためです。ECサイトでの活用例として、以下のような課題発見と改善に役立ちます。
- ・カゴ落ちの原因分析:購入直前で離脱する理由を特定し、決済フローを改善する
- ・Webサイト内回遊の促進:関連商品やおすすめ機能を強化し、顧客の滞在時間を延ばす
- ・検索機能の改善:検索キーワードを分析し、目的の商品にすぐたどり着ける導線を整える
- ・リピート購入の促進:購入履歴をもとにメールやクーポンを配信し、再購入を促す
顧客の行動を分析して課題を見つければ、効果的な改善で売上を伸ばし続けられます。
BtoB営業プロセスでの活用

ファネル分析は見込み客の獲得から商談、契約後のフォローまでのBtoB営業プロセスを可視化し、課題を特定するのに役立ちます。BtoBビジネスは検討期間が長く関係者も多いため、営業の流れが複雑になりがちです。ファネル分析を活用すればデータにもとづいて、顧客との関係が停滞している点を正確に把握できます。
BtoBの営業プロセスでは以下のような形でファネル分析が活用されています。
- ・問い合わせフォームの離脱原因特定
- ・メルマガ開封後の行動分析
- ・部門間連携の改善
- ・商談停滞箇所の分析
- ・契約後の利用状況分析
ファネル分析ではBtoB営業プロセス全体を科学的に改善し、組織全体の成約率向上と売上拡大が可能です。
SaaSプロダクトにおけるオンボーディングでの活用
SaaSプロダクトにおいて顧客がサービスを継続的に使ってくれるかどうかは、オンボーディング(初期導入体験)の質に左右されます。SaaSプロダクトにおけるオンボーディングでの活用例は以下のとおりです。
- ・新規登録から定着までの流れを可視化して離脱率を把握する
- ・離脱が多い箇所にチュートリアルやガイドを設ける
- ・オンボーディング完了率を成果測定して利用体験を最適化する
ファネル分析を導入すると顧客が登録後につまずくポイントや離脱する箇所を把握でき、適切な改善施策を打てます。
ファネル分析におすすめのツール

ファネル分析の効率を高めるには手作業を減らせるツールの導入が欠かせません。データ収集や可視化を自動化することで、ファネル分析の工程を最小限にして迅速に改善策の検討へ移れます。ファネル分析におすすめのツールは以下のとおりです。
- ・GA4 AIレポート®
- ・Google Analytics
- ・CRMツール
- ・マーケティングオートメーション(MA)ツール
GA4 AIレポート®

GA4 AIレポート®は専門的な知識がなくてもWebサイトの課題発見と改善点の特定を可能にするツールです。AIがGA4の膨大で複雑な行動データを解析し、離脱率や通過率などのファネル指標を日本語でわかりやすく可視化します。
GA4 AIレポート®なら、時間と手間のかかるデータ分析を自動化し、専門部署に頼らず自社でスピーディーな改善が可能です。AIが重要な指標を自動で抽出し、改善ポイントを一目で把握できます。
GA4 AIレポート®が提示する分析結果と人間の洞察や知見を組み合わせることで、より精度の高いファネル最適化が可能です。
Google Analytics

Google Analyticsは無料でありながら高機能なWebサイト分析ツールとして広く利用されています。ファネル分析にも対応しており、顧客の行動を段階的に把握して課題を特定するのに有効です。
最新版のGA4に搭載された「ファネルデータ探索」機能を活用すれば、顧客が目的に至るまでの経路を視覚的に確認できます。各過程での顧客数や離脱率を把握し、購入や資料請求といった目標に応じて分析経路を柔軟に設定することも可能です。
» Google「ファネルデータ探索」(外部サイト)
» Googleアナリティクスヘルプ「目標到達プロセスデータ探索」(外部サイト)
CRMツール
CRMツールとは「顧客関係管理」を支援するツールのことです。CRMツールにより顧客情報を一元管理でき、顧客との関係性を深められます。
Web上の行動だけでなくメール開封や問い合わせ履歴もCRMツールで統合できるため、顧客が離脱した段階を正確に把握できます。CRMツールを使えば顧客属性や購買履歴、行動データを組み合わせて分析し、特定の顧客層に絞ったファネル分析が可能です。
マーケティングオートメーション(MA)ツール
マーケティングオートメーション(MA)ツールは見込み客の育成を自動化し、ファネル分析を効率的に進めるのに役立ちます。MAツールで可能なアプローチは以下のとおりです。
- ・見込み客の購買意欲を点数化し、購入に近いかどうかを判断する
- ・行動や属性で見込み客をグループ分けし、最適なメールを自動で送る
- ・顧客が離脱している箇所を特定し、顧客育成の改善に生かす
MAツールはファネルの各段階で適切な働きかけを自動化し、ボトルネックの特定と改善をスムーズに進められます。
GA4 AIレポート®でできること

GA4 AIレポート®は専門知識不要でWebサイトの課題発見と改善分析ができるツールです。Google Analytics 4の膨大なデータをAIが自動分析するので、難しい操作は必要ありません。GA4 AIレポート®でできることは以下のとおりです。
- ・月次・ユーザートラフィック分析
- ・コンバージョンファネル分析
- ・AI総合分析
月次・ユーザートラフィック分析
GA4 AIレポート®は専門的な知識がなくても訪問者数や人気ページなど、基本的な指標を手軽に確認できるよう設計されています。GA4 AIレポート®の自動集計により、月次・ユーザートラフィック分析として活用できる内容は以下のとおりです。
- ・Webサイト全体の訪問状況
- ・主要な流入経路
- ・人気ページ
- ・アクセス増減の傾向
レポートは毎月自動でAIで生成されるため、分析作業にかかる時間を大幅に削減可能です。GA4 AIレポート®を活用すればWebサイトの強みと課題を直感的かつタイムリーに把握して、より効果的な改善策を打ちやすくなります。
コンバージョンファネル分析

GA4 AIレポート®のコンバージョンファネル分析は顧客がWebサイト訪問から購入・問い合わせといった行動を段階的に可視化する機能です。例えば、ECサイトにおける顧客の行動を以下のようなステップで追い、離脱が多い箇所を把握できます。
- 1.商品詳細ページの閲覧
- 2.カートに追加
- 3.購入手続きの開始
- 4.購入完了
AIが自動でファネル分析を行い、課題箇所を明確に提示するため、専門知識がなくても改善にすぐ着手できます。
AI総合分析
AI総合分析機能とはWebサイトを訪れた顧客の行動を自動で解析し、ファネル分析を含む洞察と改善策を提示する機能です。Google Analytics 4などの現代的なWeb解析ツールで提供されているAI総合分析機能では、以下のような分析・提案が行われます。
- ・指標の変化とその原因分析
- ・離脱が大きいファネル段階(ボトルネックページ)の特定
- ・各流入チャネルの貢献度分析
- ・将来のコンバージョン見込み予測
AI総合分析を活用すれば専門知識がなくてもファネル分析の結果を理解し、データを根拠とした改善策を検討できます。
» 総務省「AI利活用ガイドライン」(外部サイト)
GA4 AIレポート®を導入してボトルネックを改善しよう

GA4 AIレポート®は、専門的な知識がなくてもWebサイトの課題を特定し、改善につなげられるAI分析ツールです。GA4 AIレポート®を導入すれば複雑なファネル分析が自動化され、Webサイトの運営者が即座にボトルネックを発見しやすくなります。
流入経路や顧客の属性ごとに通過率の違いを比較することで、特定のチャネルや顧客層で発生している課題を正確に把握できます。Webサイトの改善を実施した後はAIを用いてファネルの分析を再度行い、効果を検証することが可能です。
GA4 AIレポート®は単なるデータ可視化ツールではありません。ファネル分析を中心にAIがデータを自動で解析し、次に取るべき行動を明確に示す成果につながるレポートツールです。GA4 AIレポート®を導入することで、Webサイト改善の精度とスピードを同時に高め、CVRを持続的に向上させることが期待できます。
-
お問い合わせ
SiTest の導入検討や
他社ツールとの違い・比較について
弊社のプロフェッショナルが
喜んでサポートいたします。 -
コンサルティング
ヒートマップの活用、ABテストの実施や
フォームの改善でお困りの方は、
弊社のプロフェッショナルが
コンサルティングいたします。
今すぐお気軽にご相談ください。
今すぐお気軽に
ご相談ください。
(平日 10:00~19:00)
今すぐお気軽に
ご相談ください。
0120-90-5794
(平日 10:00~19:00)
グラッドキューブは
「ISMS認証」を取得しています。

認証範囲:
インターネットマーケティング支援事業、インターネットASPサービスの提供、コンテンツメディア事業
「ISMS認証」とは、財団法人・日本情報処理開発協会が定めた企業の情報情報セキュリティマネジメントシステムの評価制度です。